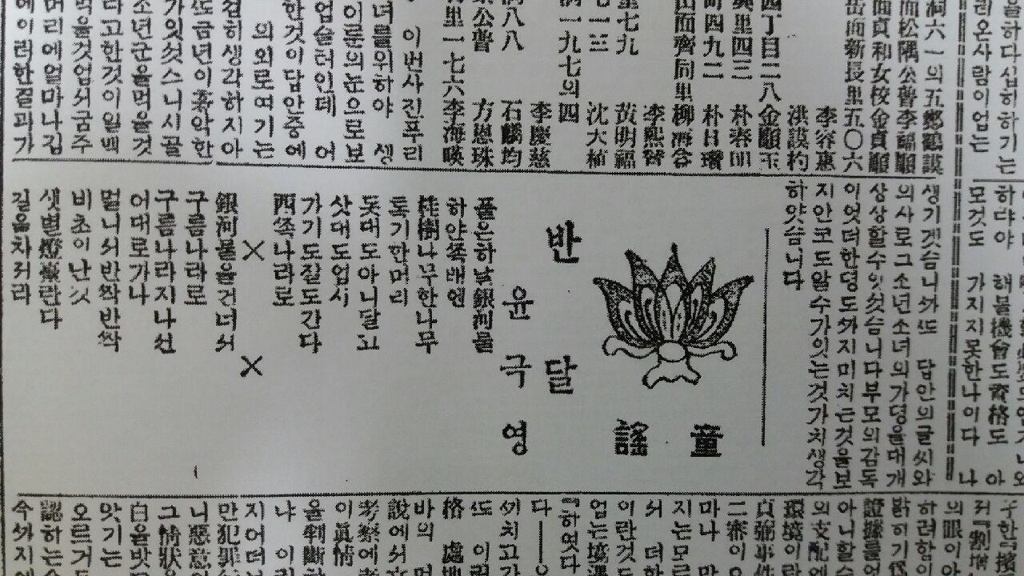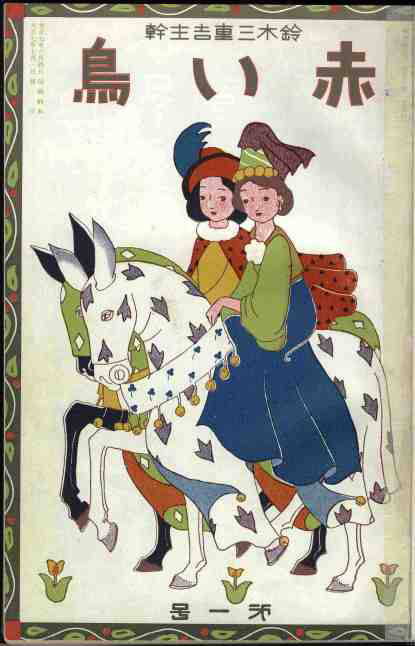なぜ「中動態」の本を読むのかと言えば、
「私」という「一人称」を森崎和江の問いがずっと、私の胸の奥深いところに刺さっているから。
妊娠出産をとおして思想的辺境を生きました。何よりもまず、一人称の不完全さと独善に苦しみました。(中略) ことばという文明の機能に重大な何かが欠け落ちている。それをどうにかしないと、私は生きられない、と、そう思いました。
一人称の不完全さと独善。by 森崎和江
「中動態」の世界を知ることは、
私たちが意識せずにそれを使って生きている<能動態>と<受動態>とが対立するものとして構成されている言語体系が、実はけっして普遍的ではないことを知ること。
森崎さん的に言えば、生きとし生けるすべての命にとって、不完全で独善的な一人称と結びついた言語体系を超える試み。
能動態⇔受動態を基本とする言語体系で構成される世界の、<外部>に思いを馳せてみること。
いったい、それはどんな世界なのか?
以下、『中動態の世界』からの抜き書き。
★もともとは、能動態と対立していたのは、中動態だった。
(受動態は、中動態から派生した。)
そして、能動態⇔受動態の世界と、能動態⇔中動態の世界は、まったく別物なのだということ。これが大事。
能動では、動詞は主語から出発して、主語の外で完遂する過程を指し示している。これに対立する態である中動では、動詞は主語がその座となるような過程を示している。(パンヴェニストによる定義 1966) p81
※出来事の「主体」ではなく、出来事の「座」というありかた。ここが大事。
ここが、何よりも私の興味を惹く。
能動と受動の対立においては、する」かされるかが問題になる。それに対し、能動と中動の対立においては、主語が過程の外にあるか、内にあるかが問題になる。(國分功一郎 p88)
◆パンヴェニストがあげる<能動態の例>
①「曲げる」「与える」
主体から発して、主体の外で完遂する過程
②「食べる」「飲む」
食べたり飲んだりしたものは、主語が占めている場所とは別のところに消える。
③「行く」「吹く」「流れる」
その指し示す動作は、聞き手のあずかり知らぬところに及ぶ。動作が主語の占めている場所の外で完結。
④ 「生きる」「在る」 これについては、後述。
◆<中動態の例>
①「できあがる」
ものが出来上がる時、そのものは生成の過程にある。
②「欲する」「惚れ込む」「畏敬の念を抱く」
誰かが何かを欲するのは、心の中から湧きおこる欲望ゆえのことであり、この欲望に突き動かされる過程の中に主語はある。
③「希望する」
人は希望しようと思って希望するのではない。不確かである未来に、しかも期待せざるをえないとき、主体をその座として希望するという過程が発生する。
※しかし、一見、中動態に分類されそうな「生きる」「在る」も能動態。
なぜこれが能動態なのか?
「在る」(存在する)は、インド=ヨーロッパ語では、「行く」や「流れる」と同様、主体の関与が必要とされない過程なのである。(パンヴェニスト)
中動態と対立するところの能動態においては――こう言ってよければ――主体は蔑ろにされている。
「能動性」とは単に過程の出発点になるということであって、われわれがたとえば「主体性」といった言葉で想像するところの意味からは著しく乖離している。インド=ヨーロッパ語では、「存在する」も「生きる」も「主語から出発して、主語の外で完遂する過程」だったと考えられるのである。(國分功一郎) p91
能動態と受動態の対立は「する」と「される」の対立であり、意志の概念を強く想起させるものであった。(中略) かつて存在した能動態と中動態の対立は「する」と「される」の対立とは異なった位相にある (中略)
そこでは主語が過程の外にあるか内にあるかが問われるのであって、意志は問題とならない。すなわち、能動態と中動態を対立させる言語では、意志が前景化しない。
(國分功一郎 p97)
「主体」が蔑ろにされている世界。あるいは、いたずらに「主体」が際立っていない世界。「意志」が問われない世界。出来事の一つの結節点(座)として主体が存在する世界。
ここから見える世界観は、実に興味深い。
さらにデリダを引用して、國分功一郎はこうも言う。
おそらく哲学は、このような中動態、
すなわちある種の非ー他動詞性をまず能動態と受動態へと振り分け、
それを抑圧することで自らを構成したのである。
デリダは態をめぐる言語の変化が、哲学そのものと内在的に結びついている可能性に言及している。すなわち、言語と思考とが関係する可能性、中動態の抑圧がいまに至る哲学の起源にあるという可能性に言及している。
(中略)
おそらく、いまに至るまでわれわれを支配している思考は、中動態の抑圧のもとに成立している。
さて、國分功一郎が中動態をめぐって語るところでは、
私たちの知る<能動態⇔受動態>という概念の中枢には動詞がある。
ところが動詞は言語の中にずいぶんと遅れて登場したのだという。
そして、動詞はもともと行為者を指示していなかった。(ここ、大事 p170)
たとえば、it rains というような非人称構文こそが、動詞の最古の形態を伝える。
「動詞の諸形態は行為や状態を主語に結びつけるもの」という現在の考え方は、けっして普遍でもなんでもないということ。「私」に「一人称」という名称が与えられているからといって、人称が「私」から始まったわけではない。「私」(一人称)が「あなた」(二人称)へと向かい、さらにそこから、不在の者(三人称)へと広がっていくイメージはこの名称がもたらした誤解である。
★言語は、出来事を描写する言語から、行為者を確定する言語へと移り変わってきた。
能動と受動を対立させる言語は、行為にかかわる複数の要素にとっての共有財産とでもいうべきこの過程を、もっぱら私の行為として、すなわち私に帰属するものとして記述する。やや大袈裟に、出来事を私有化すると言ってもよい。「する」か「される」かで考える言語、能動態と受動態を対立させる言語は、ただ「この行為は誰の者か?」と問う。
ならば次のように言えよう。中動態が失われ、能動態が受動態に対立するようになったときに現われたのは、単に行為者を確定するだけではない。行為を行為者に帰属させる、そのような言語であったのだと。出来事を描写する言語から、行為を行為者へと帰属させる言語への移行――そのような流れを一つの大きな変化の歴史として考えてみることができる。 p176
一方、「出来事」を中心に考えるのならば、
出来事は能動的でも受動的でもない。
出来事に先立って、主語はない。
出来事こそが言語を可能にする。
そして、その出来事を最初に名指すのが動詞である。
(そして、その動詞とは、そもそもは能動でも受動でもなく、中動だったのだろう。主体は出来事の内にあるのだから。)
これは能動態と受動態に支配された言語を疑った哲学者のひとりであるドゥルーズの思考を、國分功一郎が簡潔な言葉でまとめているもの。
(ほかにもハイデッガー、アレントについて國分功一郎は触れている)
そして、中動態を考えるにあたって最重要なのが、スピノザ。なぜなら、スピノザの構想する世界は中動態だけがある世界だから。
①あらゆるものは神の一部であり、また神の内にある。
②神とはこの宇宙、あるいは自然そのものに他ならない。「神即自然」。
神すなわち自然という実体がさまざまな性質や形態を帯びることで個物が現われる。
神すなわち万物の原因である。
つまり
★ 神に他動詞はない。
(神が何事かを働きかける他者はこの世界には存在しない。)
★ 神に受動はありえない。
(神には外側はない。外側がない以上、神に影響や刺激を与えるものはない)
★ 完全に能動たりうるのは神のみである。
★ 神という唯一の「実体」の変状の結果としての「様態/個物」がある。
(人も石ころも樹木も神の態様の一つ)
★ 個物は互いに影響し合い、刺激し合い、変状する。
だが、そこには、私たちの知る<能動―受動>の関係性はない。
スピノザの考える因果性、中動態において捉えられた因果性の概念においては、原因は結果において自らを表現するのだった。ならば、われわれが自閉的・内向的と呼んだ中動態的な変状の過程も、この因果性によって説明できるはずだ。すなわち、この因果性の概念によるならば、欲望の結果として現れる行為や思考は、その原因である力としての本質を本質を表現していることになる。
(中略)
われわれの変状がわれわれの本質によって説明できるとき、すなわち、われわれの変状がわれわれの本質を十分に表現しているとき、われわれは能動である。逆に、その個体の本質が外部からの刺激によって圧倒されてしまっている場合には、そこに起こる変状は個体の本質をほとんど表現しておらず、外部から刺激を与えたものの本質を多く表現していることになるだろう。その場合にはその個体は受動である。
(中略)
一般には能動と受動は行為の方向として考えられている。行為の矢印が自分から発していれば能動であり、行為の矢印が自分に向いていれば受動だというのがその一般的なイメージであろう。それに対しスピノザは、能動と受動を、方向ではなく質の差として考えた。
そして、中動態の世界における<能動>と<受動>を、スピノザの哲学ではこう言い換えられている。
<自由>と<強制>
「自己の本性の必然性に基づいて行為する者は自由である」
「強制されているとは、一定の様式において存在し、作用するように他から決定されていることを言う」
------------------------------------------------------------------------------------
さて、
私が「中動態」の世界を想う時、
そこには「語り」の世界がある。
「声」が開く場がある。
「場」の声としての「語り」がある。
脈々とつらなる命の世界の声としての「語り」がある。
能動と受動、所有の一人称、支配の一人称が起動する世界に「穴」をあける声としての「語り」がある。
中動態。
キイワードは「出来事」。
支配と強制からの自由。
キリスト教を踏まえつつ、神すなわち自然という世界観から語られる、
その意味では、すべての存在が、この世界という「出来事」を織りなし、脈々ととながっている、スピノザ的世界とその「中動態」は、ストンとおちてくる。
出来事の世界に生きる者にとっての「自由」。それもストンとおちてくる。
それは私的所有をする者、支配をする者の自由とは異なる。
支配される者の奴隷の自由とも異なる。
ましてや、新自由主義の自由などでもない。
命がその本質を表現しうること。
つまりは、命が命として尊ばれること、「自由」な命のありようを基本とすること。
われわれが、そして世界が、中動態のもとに動いている事実を認識することこそ、われわれが自由になるための道なのである。中動態の哲学は自由を志向するのだ。
(國分功一郎 p263)