11月16日から始まった森崎和江の旅をたどりなおす旅。
今回の旅の出発点は宗像・鐘崎であったけれど、
本当の出発点は、朝鮮なのである。
そのことを胸に刻みつつ、森崎さんの詩集「地球の祈り」を再読する。
むかしのその詩集(『かりうどの朝』)のあとがきに、「私は、詩とは、本来、他者とのダイアローグであると考えていた。自分以外の、自然と人々との」と書いています。この思いは今もかわりません。
しかしダイアローグということばは不十分です。私は、子どもの頃から鉛筆やクレパスをおもちゃにして一人遊びをしていました。そして、いつしか、心やからだに響いてくる自然や人や生きものとの、共振ともいえる世界を感じていたようです。それはかつての朝鮮で生まれ育った私が、話しことばのちがう人びと―――朝鮮や中国やロシアやヨーロッパの人たちもいました――の、大人たちをも、ちいさくちいさく思わせるほどの美しさと広さで、朝や夕方の空が色調を変えることに心打たれ、ぽろぽろ涙をこぼしていたことなどと関連していると思います。小学校入学前後から、しばしば、そうした体験をくりかえしました。
その、自然界といのちとのシンフォニーへの愛をはぐくんでくれたのが、「日帝時代」の大地であったこと、また、その大地に響きわたっていた歌とリズムであったことが、つらくて、幾度となく崩れました。それでも類似する苦悩は地球上に満ち、歴史に刻まれ、姿をかえてつづきます。
それでも、表現とは、自分と外界との響きあいを、ことばや音や色や形へと対象化させることだと思いつづけてきました。というよりも、生きることとは本来そういうものなのだと考えるようになってきました。(詩集『地球の祈り』あとがきより)
旅の出発点として、このあとがきを読む。
さらに、森崎和江の朝鮮での原体験を『慶州は母の呼び声』あとがきから引いてみる。
朝鮮語では母親のことをオモニという。わたしという子どもの心にうつっていた朝鮮は、オモ二の世界だったろう。個人の家庭というものは広い世界の中に咲く花みたいなもので、世界は空や木や風のほかに、沢山の朝鮮人が生きて日本人とまじわっているところなのだと、そんなぐあいに感じていたわたしは、常々、見知らぬオモニたちに守られている思いがあった。つまり、それほどに、朝鮮の母たちの情感はごく自然に大地に息づいていた。わたしは行きずりのオモニから頭をなでられ、小銭をにぎらせようとされ、ことばもわからぬままかぶりを振って、まだ若かった母のきものの袖にかくれたものである。(中略)異質さの発見と承認も、わたしはオモニによって養われたのである。
植民地朝鮮には、帝国日本とは異なる産土の神がいて、近代日本とは異なる風土があり、その風土で草木のように育まれた死生観や他者との交わりを生きる共同体があり、神と共に歌い踊る祭があり、そのなかに朝鮮の支配者の子であった森崎和江は孕まれ育まれたのだった。
自身の生のもっとも本質的な部分が、他者の風土を侵して、その風土を貪って、形作られたことを知った時の森崎の衝撃。生涯拭いがたく胸に刻まれた原罪意識。
近代日本の子として、植民者の子として、知らず知らず他者の「いのちの母国」を侵す(=犯す)ことが自身の生の出発点であることの<取り返しのつかなさ>。
自身が侵した他者に出会い直すためには、自身の「いのちの母国」を探しあて、生きなおさねばならないである。
他者の「いのちの母国」を貪り、消し去ろうとしてきた近代の思想、近代の言葉では、けっして「いのちの母国」にはたどり着けない、生き直しはできない、死ぬことすらできない。そのことも森崎和江にはよくわかっていた。
いのちの思想、いのちの言葉(それを森崎は「産みの思想」と呼ぶ)をつかみとるために、一時期共に闘うことを選んだ谷川雁との決別は、一つの命が強姦(他者を侵す=犯す)ということで奪われたことに対して、その一つのいのちに向き合うことよりも、闘いのための組織を守ることを優先させたことに、まさに森崎が越えようとしていた近代的な論理を見たから。
宗像から海沿いに「いのちの母国」を探し求めて、津軽まで北上していく旅『海路残照』。
そのはじまりは「八百比丘尼伝説」それについて、森崎は小浜で催された「八百比丘尼サミット」で下記のように語っている。

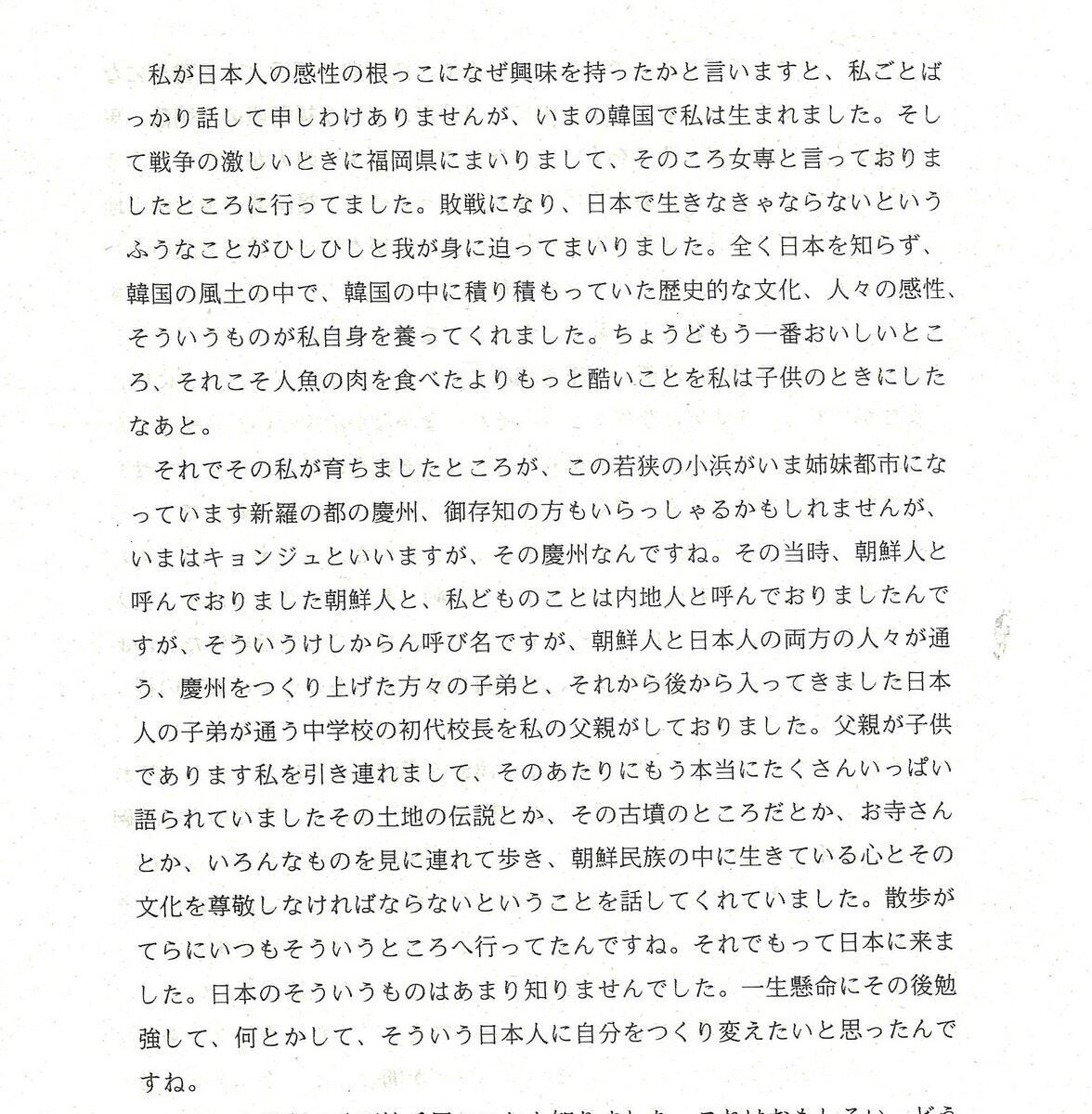
森崎和江は、食べてはならぬ禁断の「人魚の肉」を食べたことで不老不死となり、旅を生きざるを得なくなった八百比丘尼の運命を、朝鮮を貪って同じく旅を生きざるを得なくなった自身の運命と重ね合わせて語っている。
しかし、この旅は困難な旅。
日本列島自体が、近代の論理によって、近代の神々とは異なる産土の神が消され、産土に宿っていた死生観、他者との交わりに対する感性が塗りつぶされてきたから。近代の神々の体系が日本列島を覆いつくしたから。
生まれくるいのち(これもまた他者である)をいのちのままとして生かしていく心情や感性や思想を喪い、国家や権力の礎としての死を讃える、いわば<死の体系>の上に成り立つ社会や国家に人々は飲み込まれていったから。
おおらかに命の到来を讃え、去りゆく命を心から悼む、ただその命のために。
自他の境をこえてこそ、なつかしい死者たちとともに共に生きてこそ、生者も生かされるのだということを、いまだきっと失わずにいるその心情を、感性を探し求めて、
その心情や感性とともにある、近代の神々の体系とは異なる、産土の神(=異神)との出会いを求めて、
産土の祭をいまだ心に宿している人々を訪ね歩いて、
奪われた風土の記憶を、奪っていった者への抗いの記憶を、かすかなりとも身の宿す者たちを訪ね歩いて、
近代の論理によって、チリヂリバラバラに分断されていくいのちの風景を結び直しながら、
森崎和江は旅をする。
旅の途上で斃れた者たちと共に。
風土を踏みしめ、魂の鎮魂と風土(いのちの母国)のよみがえりを念ずるように、あたかも反閇をしながら、道をゆくかのように。
炭鉱という地の底、鐘崎海女、八百比丘尼の故郷小浜、そして化粧地蔵を丁寧に祀ってきた津軽の人びと、北上の反閇する者たち、
その一つ一つが異神との出逢いであり、近代とは異なるいのちの風景の中に分け入ることである。
森崎和江は、旅で、その足で、文字にはならぬ「いのちの声」「いのちの音」を結んでいって、いのちの思想をつむいで、いのちの母国へとたどりつく、
うけつぐべきは、森崎が辿り着いたいのちの母国ではなく、おのれのいのちの母国、(これをいのちの原郷と呼んでもいい)へと、旅を生きるその生のありよう。
森崎和江を孕むのである。
そうして旅するわれら一人一人が、ひとりひとりの命の母国を目指して歩きはじめるとき、はじめて、森崎和江のいのちの思想は受けつがれてゆくのだろう。
旅せよ! 予め失われ、予め断ち切られたいのちを生きる、われら近代の民!